| ※最新ニュース 令和3年02月07日に取材してきました。「那珂川の渡し跡巡り」勝倉舟渡跡 |
| ぐるり自転車De橋めぐり | | 水の都(みと) |
| 那珂川 逆川 | 内川 桜川 | |
  
  
   |
| 常磐高速鉄橋 駅南出会橋 | 水門管理橋 新桜川橋 | |
| 国田大橋 駅南中橋 | 留の橋 新町橋 | |
| 千歳橋 舟付橋 | 内川橋 仲ノ橋 | |
| 万代橋 逆川橋 | 出合橋 搦手橋 | |
| 水府橋 本郷橋 | 内川橋 石垣橋 | |
| 水郡線鉄橋 ふれあい橋 | 境川 水門橋 | |
| 新・寿橋 小門橋 | 境川橋 柳提橋 | |
| 水戸大橋 水神橋 | 田谷川原橋 駅南小橋 | |
| 常磐線鉄橋 塩橋 | 門前橋 駅南大橋 | |
| 勝田橋 新米沢橋 | 第二境橋 美都里橋 | | 偕楽園(かいらくえん)
|
| 東水戸道路橋 米沢橋 | 西田川 千波大橋 | | 正式には常磐公園と称する国指定史跡・名勝だが、一般的
|
| 沢渡川 笠原橋 | 古川橋 芳流橋 | | には偕楽園と呼ばれている。
|
| 花追橋 第二米沢橋 | とろんこ橋 偕楽橋 | | 岡山の後楽園、金沢の兼六園と並んで、日本三名園の1つ
|
| 猩猩橋 中水門橋 | 西田橋 田鶴鳴橋 | | に数えられ、とくに梅の公園として知られている。
|
| 桜山新橋 第三米沢橋 | 藤井川 窈窕橋 | | 水戸藩主徳川斉昭が1842年(天保13年)7月開設し
|
| 桜山橋 石川川 | 上合橋 梅郷橋 | | た偕楽園が主体で、見川町にある桜山と丸山はその付属地
|
| 新沢渡橋 石川川橋 | 藤井大橋 好文橋 | | である。園中の好文亭・奥御殿・吐玉泉などが有名。
|
| 沢渡橋 上組橋 | 藤井新橋 春秋橋 | | 楮川(こうぞがわ)ダム
|
| 弁天橋 上石川橋 | 工兵橋 矢の目橋 | | 昭和61年に完成した、水道専用ダム。渡里町の導水ポン
|
| 石川橋 名称不明 | 上入野橋 江戸道橋 | | プ場から貯水池へ原水を汲み上げたのち浄水して配水タン
|
| 堀原橋 石川橋 | 田野川 桜川橋 | | クから市内に給水される。付近には、市民野球場や浜見台
|
| 遠下橋 元石川橋 | 長者橋 桜川団地橋 | | 霊園墓地などがある。
|
| 野田橋 柏渕橋 | 田野川橋 若林橋 | | 重力式コンクリートダム
|
| 水門橋 森戸橋 | 下田橋 八幡橋 | | 高さ35m、長さ364m
|
| 新中丸橋 入野橋 | 東橋 高天原橋 | | 総貯水量1.970.000立方m
|
| 備前堀 中井川橋 | 田野川橋 氏神橋 | | 那珂川(なかがわ)
|
| 伊奈橋 石川橋 | 別当橋 栄橋 | | 栃木県那須郡那須岳が上流端。途中で余笹川・箒川・緒川
|
| 荒神橋 三又橋 | 中央橋 境橋 | | ・藤井川などを合流し、さらに桜川、河口では涸沼川をも
|
| 鎖魂橋 新川 | 北川橋 榎戸橋 | | 合流して太平洋に注ぐ。
|
| 道明橋 名称不明 | 中橋 湯漉木橋 | | 幹川延長149.7km。
|
| 三又橋 名称不明 | 逢関橋 | | 支流数60。
|
| 学の橋 鹿島橋 | 鶴巻橋 旧桜川 | | アユの観光やな場やサケの遡上が有名。
|
| 金剛橋 渋井橋 | 狭間川 丸山橋 | | 吐玉泉(とぎょくせん)
|
| 常陸山橋 境橋 | 大山橋 新坂橋 | | もともと湧き水の多い地区で、眼病に効くといわれていた
|
| 常陸山橋 吉野橋 | 名称不明 城跡橋 | | 。偕楽園造成にあたり、その湧き水を茶室の茶の湯に供す
|
| 旧酒門橋 極楽橋 | 沓掛橋 名称不明 | | るとともに、造園上の添景を考慮し白色の泉石を据え、特
|
| 小塙橋 | 滝下橋 | | 殊な工法を施した湧水泉を建造したもの。
|
| 那珂川の渡し跡巡り | | 現在の泉石(常陸太田市真弓山の大理石)は昭和62年に
|
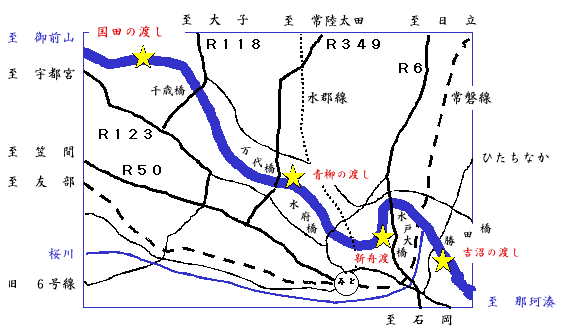 | | 設置。
|
| | 大塚池(おおつかいけ)
|
| | 江戸時代より旧笠間街道一の風景といわれ、茨城百景にも
|
| | 選ばれている。かつては周辺の水田に水を引く、ため池と
|
| | して利用されていたが現在は、野鳥などの生物も多く、冬
|
| | には白鳥も飛来する公園となっていて、池の周囲には約2
|
| | .6kmの遊歩道がある。
|
| | 別名を新堂池という。
|
| | 桜川(さくらがわ)
|
| | 東茨城郡内原町有賀を上流端として、途中、狭間川と沢渡
|
| 国田の渡し | 国田の渡しは那珂川をこえて水戸 | | 川を合流したのち、千波湖の水も加える。
|
| | 城下に入る数ヶ所の渡しのひとつ | | 東岸では逆川も合流する。さらに下流で、備前堀に水を供
|
| 国田大橋の下流約650m地点 | である。江戸時代に軍事上の必要 | | 水したのち那珂川に注ぐ。延長13km。
|
| 堤防外脇(枝内取水塔対岸) | から一般に橋をかけず渡渉また舟 | | 桜の名所を通ることから、「桜川」と名付けられた。
|
| 千歳橋の上流約2510m地点 | を使わせたが、水戸城下でも渡河 | |
|
 | の規制はきびしかった。また、渡 | | 千波湖(せんばこ)
|
| し賃は享保三年(1718)の規 | | 桜川河口の土砂堆積でせき止められてできた湖。江戸時代
|
| 定によると通常の水量の時で一人 | | には、水戸城要害をなし、長さ3.5km、幅0.7km
|
| 二文、から馬三文、荷物をつけた | | 、水深1.8mあったが、大正末期に干拓され、面積が3
|
| 馬五文とあり、悪天候の時は上乗 | | 分の1程度に狭まった。
|
| | せされた。 | | 現在は、東西1250m、南北350m、平均水深1m。
|
| 青柳の渡し | この地には昔から青柳の渡しと呼 | | 別名(千波沼、仙波湖)
|
| 万代橋の下流約230m地点 | ばれた渡船場があって対岸の海老 | | 笠原水源(緑地)
|
| 旧道ガードレール脇 | 窪風呂の下との間に渡し船が往来 | | 笠原水道は水戸藩第二代藩主徳川光圀の命により、下町(
|
| 水府橋の上流約1220m地点 | した。しかし水戸藩は城に近いた | | 現在の下市周辺)の水不足解消のため、延べ2万5千人の
|
 | めに夜船番所を置き藩の重臣以外 | | 人手を費やして、寛文3年(1663)に完成した。水道
|
| は夜の渡船を厳しく禁止していた | | は暗渠となっていて、樋の材料には、岩・木・竹・銅など
|
| 。明治以後は禁制が解かれ両岸に | | が使用された。総延長約10kmで、約250年間下町の
|
| 漕手の船番と料金を扱う箱番があ | | 人々を潤した。
|
| って客がたまると船を出したが大 | | 備前堀(びぜんぼり)
|
| | 正八年万代橋ができてから渡船は | | 1610年(慶長15)関東郡代 伊奈備前守忠次によっ
|
| 新舟渡の跡 | 廃止された。 | | て造られる。
|
| 水府橋の下流約1930m地点 | はじめやや上流にあった舟渡は寛 | | 当時、千波湖から取水していた用水路で水田に水を引くと
|
| 堤防外側道路角部分 | 永の末年下町が開発されるとこの | | ともに、桜川の氾濫による下市(しもいち)地区の洪水を
|
| 水戸大橋の上流約280m地点 | 地に移されて新舟渡と呼ばれた。 | | 防止するため造られた。別名を伊奈堀ともいう。
|
 | 陸前浜街道は細谷からこの新舟渡 | |
| を経て対岸の枝川に通じたので水 | | 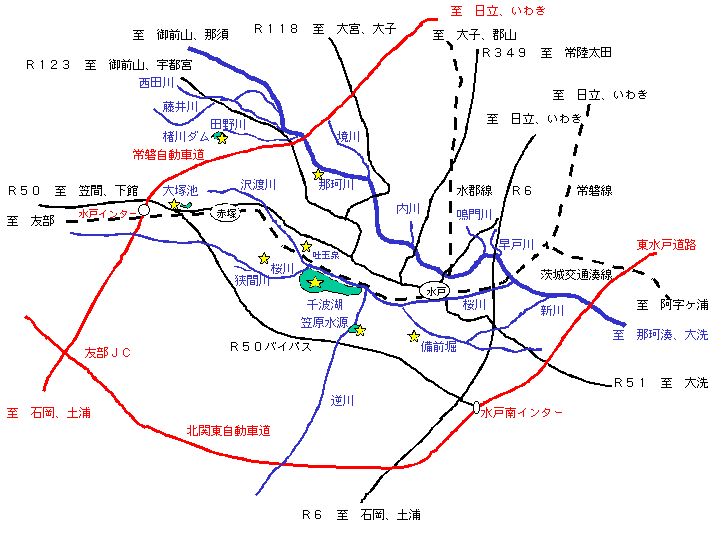 |
| 戸藩時代の新御蔵南には重臣の蔵 | |
| 屋敷が置かれ、枝川には宿屋が並 | |
| んでいた。渡船は規定によって統 | |
| | 制されていたが大正元年寿橋がで | |
| 勝倉舟渡跡 | きて廃止された。 | |
| 水戸市吉沼町の勝田橋対岸にある | (以上は水戸市側にある石碑) | |
| ひたちなか市側最初の交差点を右 | | |
| 折した土手づたい約50mにある | 対岸の吉沼とつながる勝倉の渡し | |
 | は舟渡と呼ばれ住吉から村松街道 | |
| と浜街道を結ぶ交通の要所であっ | |
| た 江戸時代には那珂川を利用し | |
| て米・薪・干鰯などを輸送する水 | |
| 運が発展し流域に河岸が設けられ | |
 | た 勝倉河岸は天保年間に創業 | |
|
| 荷物は薪を主としたことから薪河 | | 那珂川の治水事業により往年の貴重な街並みも姿を消す
|
| 岸と呼ばれた 船渡には旅籠 茶 | | に至り ここに記念碑を建立し後世に伝えるものである
|
| 屋 船頭長屋が軒を並べ賑わいを | |
|
| 呈した 水戸藩の船番所も置かれ | |
|
 | た 繁栄した船渡も近代になり鉄 | | 平成十六年三月設置
|
| 道路の発達によって 昭和初期に | | ひたちなか市教育委員会
|
| 水運は衰退し 渡し舟も昭和25 | |
|
| 年勝田橋の完成に伴いその役割を | |
|
| 終えた | |
|